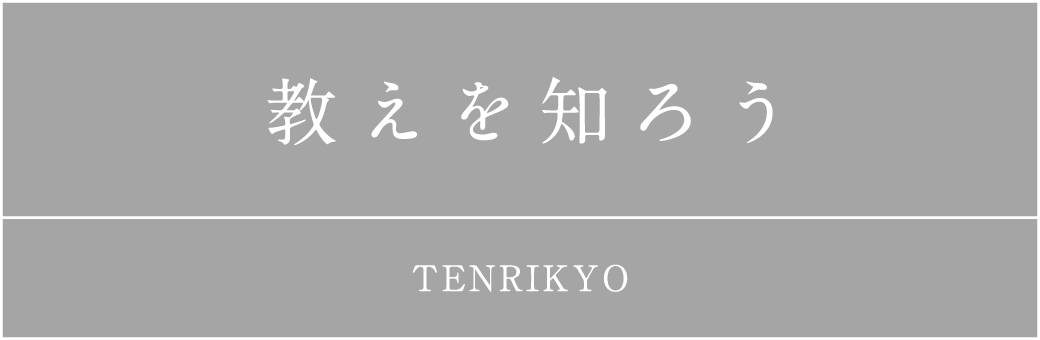
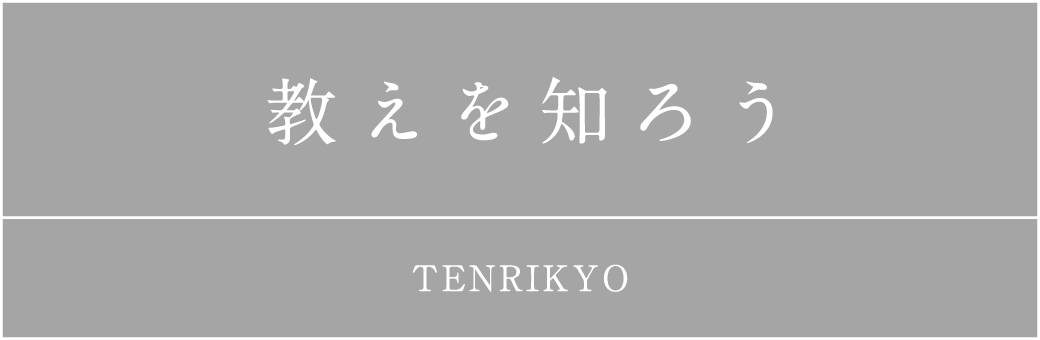

だれもが自分のものであると思って使っている身体を、親神様からの「かりもの」と教えられます。そして、心だけが自分のものであり、その心通りに身の内をはじめとする身の周りの一切をご守護くださるのです。
これを、
「人間というものは、身はかりもの、心一つが我がのもの。たった一つの心より、どんな理も日々出る」(おさしづ明治22年2月14日)
と仰せになっています。
従って、借りものである身体は、貸主である親神様の思召に適う使い方をすることが肝心です。この真実を知らずに、銘々に勝手気ままな使い方をすることから、十全なるご守護を頂く理を曇らせ、ついには身の不自由を味わうことにもなってきます。
この思召に沿わぬ自分中心の心遣いを「ほこり」にたとえ、不断に払うことを求められます。
また、親神様の自由のご守護に与ることのできる心遣いは誠の心であり、その最たるものは「人をたすける心」であると教えられます。
「借りる」とは「他人のものを、あとで返す約束で使う」(『広辞苑』)ことです。従って、かりものである身上(身体)は、いずれはお返しすることになります。これが出直しです。
そして、末代の理である銘々の魂に、新しい身体をお借りしてこの世に帰ってくることを、生まれ替わりと教えられます。
「思うようにならん/\というは、かりものの証拠」(おさしづ明治21年7月28日)
とあるように、病んで初めて身体が自分の思い通りにならないことを知ります。
「たん/\となに事にてもこのよふわ
神のからだやしやんしてみよ」(第三号四十、百三十五)
「にんけんハみな/\神のかしものや
なんとをもふてつこているやら」(第三号四十一)
との「おふでさき」にうかがえるように、かしもの・かりものの教理の背景には、この世は神の身体という世界観があります。すなわち、神の身体であるこの世の一部をわが身の内としてお借りしているのです。従って、世界と人体は一つの天の摂理に支配されていることになります。
道友社刊『ようぼくハンドブック』より